Characters
††:未発表曲・レア曲集
†††:ベストアルバム
††††:ライブアルバム
†††††:その他のアルバム

Candlebox(キャンドルボックス)の母体となったUncle Dukeがヴォーカリストのケヴィン・マーティンとドラマーのスコット・マーケイドによって結成されたのは1991年の5月頃であった。彼らが出会ったのはケヴィンがシアトルの高校を卒業した1989年前後の時期だったが、すぐにバンドを組んだというわけではなかった。1991年の9月にはギタリストのピーター・クレットがUncle Dukeに加入し、11月には別のバンドにいたベーシストのバーディ・マーティンを加えてセッションを行った。そして12月にはバーディが正式に加入し、ここにバンドのラインナップが完成する。後に彼らの代表曲の1つとなる"You"はその日の夜に書かれたものだという。その後、バンドはMidnight Oil(オーストラリアのロックバンド)の"Tin Legs and Tin Mines"の曲の歌詞の一節("boxed in like candles")からヒントを得て、バンド名をCandleboxへと変更する。
ヴォーカリストのケヴィンがテキサス州の出身であることから、彼らはしばしば「グランジブームに乗ってデビューするために、ムーブメントの拠点であるシアトルに引っ越してきたバンド」と揶揄されることがある。しかしケヴィンがシアトルに引っ越してきたのは1985年で、彼がまだ14歳のときの話である。また当時はグランジもシアトルのアンダーグラウンドシーンでのみ注目される存在でしかなかった。ちなみにドラムのスコットは1歳の頃から、他の2人は生まれたときからシアトルで暮らしていたとのことである。
彼らはバンドを組んだものの、シアトルのミュージックシーンとの密接な関係を持っていたわけではなかった。そこで彼らはシアトルでライヴを行うために、まずデモテープを作ることに着手する。彼らは皆でお金を出し合うことでBob Lang Studios Easterというレコーディング・スタジオを借りるが、得られた時間はたったの48時間だけであった。彼らは自分達の友人であり、シアトルのバンドを手伝っていたケリー・グレイをプロデューサーに迎えてデモテープのレコーディングを行う。当初は3曲のみの予定だったが、作業は順調に進み最終的には8曲をレコーディングすることに成功する。このデモテープは600本作られ、2ヶ月で完売することとなる。ここで録音された"Far Behind"と"You"はそのまま彼らの1stアルバム"Candlebox"にも収録されている。
デモテープをきっかけに知名度を増してきたCandleboxは、BMI主催のショウケースで25分間の演奏を行い、メジャーレーベルからも声がかかるようになる。彼らは興味を示してきたレーベルのために、ロサンゼルスでEMI主催によるショウケースで演奏を行い、そこで21歳のA&Rマンであるガイ・オシアリーの目に留まり、(Warner Brothersの支援を得てマドンナが設立した)Maverick Recordsと契約を結ぶこととなった。

バンドはシアトルのLondon Bridge Studiosに入り、1993年の3月からデモテープのときと同じくケリー・グレイをプロデューサーに迎えてレコーディングを開始する。デモテープに収録された曲の再レコーディングを4曲と、デモテープの収録テイク2曲("You"と"Far Behind")などを含む1stアルバム"Candlebox"を7月にリリースする。
ダークでグルーヴィー、そして適度に土臭さを感じさせるサウンド。本作におけるCandleboxの音楽性はある意味ではいかにもグランジ的と形容することができよう。しかし彼らのダークネスは多くのグランジ勢のようにBlack SabbathやBlack Flagに由来してはおらず、Led Zeppelinやブルーズからの影響が大きい。言うなれば70年代のブルージーなハードロックに90年代の手法やグルーヴを持ち込んだといった類のものである。彼らと共通性を持ったバンドとしてはPearl Jamが挙げられるだろうが、そのうねりの質やヴォーカルスタイルには大きな違いがある。本作に見られるうねりや重さは、Pearl JamやSoundgardenのような渦の中に飲み込んでいくかのような感覚は弱く、もっとオーソドックスなハードロックのドライヴ感に近い。またヴォーカルもやや高いトーンの声質にLed Zeppelinのロバート・プラントの影を感じさせるようなスタイルであり、力強く押し込んでくるといったタイプではない。また、その声からはMother Love Boneのアンドリュー・ウッドを想起する人も少なくないようだ。
#1の"Don't You"はアルバムの中で最もグルーヴィーで、オープニングを飾るにふさわしい曲だ。Pearl Jamの1stアルバム"Ten"に収録されている"Once"とそのうねりの質の違いを比較してみるのも面白い。#2と#3はブルージーな空気を漂わせつつ、サビで一気に爆発する強弱法を踏襲した、このアルバムの音楽性が最もよく表れている曲だ。特に#3の"You"は後半にかけて感情を急激に高めて放射する熱度の高さを見せつける。#4は#2と似た雰囲気の曲ではあるが、感情はかなり抑制され、ギターソロをはじめとして深みのあるブルージーなトーンを前面に出している。続く#5の"Far Behind"と#6は90年代的な要素を持ちながらも、もっと純然たるアメリカンロックを感じさせる。Pearl Jamの持つ乾いた砂の香りや、Stone Temple Pilotsの焼け付く大地のような感触とも異なった、アメリカの古風な町を思い起こさせる大らかさを備えている。
#7の"Arrow"からアルバムは新たな局面に入り、実験性も含んだ起伏のある展開を見せていく。#7は#1にも似たハードな曲だが、#1よりももっとオーソドックスなハードロックのドライブ感を持っている。続く#8はまさにブルーズ・ハードロックそのものといった曲で、バンドの音楽的な基盤がどこにあるのかを雄弁に物語る。#9は次作の"Lucy"の路線を示唆するかのようなオルタナティブ色の強い実験的な楽曲だ。全体的にやや落ち着いた雰囲気を持ったこのアルバムの中において、この曲の持つ狂気のインパクトは大きい。ヘヴィネスを重視した"Lucy"のサウンドプロダクションで聴いてみたいとも思わされる。そしてアルバムは静と動のコントラストが美しい#10へと続く。#2の路線とアコ・アプローチを融合させたこの曲は、より深い部分での感情の動きを映し出してくる。#11はアコースティックスタイルの曲で、#10からの流れを受け継ぎ、1つの旅が終焉を迎えるかのごとくアルバムを締めくくっていく。
歌詞は全体的に抽象的で独り言のようなものが多い。1人の相手に語りかけるようなものも少なくないが、それも自分の世界に入ってずっとつぶやくような感じである。#1~#5はどれもそういったスタイルで書かれており、#8はまるで酔っ払いが延々と愚痴を言い続けているかのようである。しかし、その中でもドラッグに溺れた友人に対する思いを畳み掛けるように語る#3は、その感情の高ぶりが上手く表現されている。また、#7までの歌詞は冷静さを感じさせるが、#8からはそこに強い混乱が見られるようになる。#9と#10では内面的な葛藤が自問自答のように書かれる。#11では住む場所を失い、1枚の毛布を「家」と呼んで暮らす男と自らを重ね合わせる姿が描かれている。社会的な側面を持った歌詞というよりは、もっと個人的な視点で書かれた印象が強い。
総合的に見れば拙さを感じさせてしまう面もあるのだが、アルバムの流れが非常にスムーズなため、最後までサラリと聴かせてしまう力がある。ハードロックのドライブ感に90年代的な要素、それにブルーズが未完成なまま融合されているとも言えるが、それによって逆に各々の素材の旨味がそのまま活かされているという良さもある。音楽性の成熟という点では次作以降に譲らざるを得ないが、ブルーズ・ハードロックとしての魅力が最も発揮されているのは本作であろう。

1stアルバム"Candlebox"リリース後の8/25に、Candleboxは地元シアトルからツアーを開始し、10/9からはGreta、Living Colourとの全米ツアーを行う。また、1994年の1/22からはRushのツアーのオープニング・アクトを務めるなど、積極的なライヴ活動を行った。
また、1993〜1994年にかけて"You"と"Far Behind"のビデオがMTVでくり返しオンエアされるようになる。それによってアルバムはセールスを伸ばし、最高位として7位をマークするなど、最終的に400万枚を超えるヒットを記録する。さらに彼らはMetallicaやFlaming Lipsらともツアーを行い、Woodstock '94のメインステージにも登場、David Letterman Showでのライブパフォーマンスなども行った。彼らは映画"Airheads"のサウンドトラックに1stアルバムからのアウトトラックである"Can't Give In"を提供。このサウンドトラックは1994年の7/19にリリースされることになる。
1995年の3月には前作と同じくプロデューサーのケリー・グレイと共にLondon Bridge Studiosへと入り、新作のレコーディングを開始する。アルバムのレコーディングは5月に終了し、彼らの2ndアルバムとなる"Lucy"は10月にリリースされた。
1stの"Candlebox"に比べてよりグランジ色が強まったと言われることの多い本作。そのように聞くと、「よりPearl Jamっぽくなった」と捉えられがちだが、実際には前作よりも土臭さはかなり減退している。「グランジ」と呼ばれる音楽性はAlice In ChainsのようなBlack Sabbath直系のものから、MudhoneyのようなThe Stoogesの原初的なガレージパンクの影響下にあるサウンドまで、かなりの幅の広さを持っている。本作"Lucy"においてCandleboxが接近したのは、「ダークでヘヴィなギターロックとしてのグランジ」という類のものである。そのサウンドはラフでルーズ、そして横に揺られるようなうねりが強くなり、ヘヴィロックとしての主張はより強まっている。サウンドプロダクションもヘヴィネスをより強調しており、とりわけベースが重みを増して迫ってくる。一方で1stで見せた70年代的なハードロックの息遣いは弱まったが、彼らの基盤でもあるブルーズは本作においても重要な位置を占めている。
ギターロックの色合いが濃厚なグランジというと、Nirvanaからの直接的な影響を強く匂わせるサウンドが多い。しかしながら、本作におけるCandleboxの音楽性はギターロックに接近しながらもその底流にはブルーズがあり、ときにパンキッシュな顔を覗かせながらも独特の叙情性を帯びている。ブルーズとギターロックという音楽的な隔たりが大きいと思われる2つの素材を、違和感なく1つのキャンバスに溶け込ませたことは見事と言えよう。異素材がゴツゴツとぶつかり合っていた印象の強い前作とは比較にならないほどの音楽的なまとまりが表れている。
アルバムは本作で得た諸要素が最大限に発揮された"Simple Lessons"で幕を開ける。うねりのあるグルーヴとヘヴィネス、ブルーズとパンキッシュなギターロックの融合というスタイルの完成形と言ってもいいだろう。前作の"You"を彷彿とさせる感情の放射を見せ、シンプルな強弱法のスタイルを越えた形での静寂と狂気の対比を強烈に叩きつけてくる。そして、このアルバムで最もパンキッシュかつアグレッシブな姿を見せるのが#4と#8だ。#4はひねくれたポップ感を持ったメロディと疾走感のあるサウンドとが絡み合っている。その中にもやはりブルーズの影響を覗かせるなど、Candleboxにしか出せない個性が引き出されている。それに対して#8はポップな質感は弱く、ストレートな攻撃性が前面に出ており、ひたすらに刃物で切り込んでくるような鋭さがある。アグレッシブな曲であっても、1stに収録されていた"Arrow"とはその志向性は大きく異なっている。
この3曲を除けば、アルバムは攻撃性よりも内省的な叙情性を帯びた、落ち着いた曲が中心となっている。それがゆえに「淡々としている」と評されることもあるだろうが、彼らのサウンドに流れるブルーズの旨みがあるため、退屈さを感じさせられることはほとんどない。#2はアルバムの中でも中庸的な立ち位置の曲であり、爆発するような勢いを抑え込みながら、複雑な感情の揺れを巧みに表現する。また、ノイジーなギターソロによって混沌が描きあげられていく様も素晴らしい。#3は#2よりもさらに抑制された感のある曲だが、つぶやくようなヴォーカルから始まり、後半にかけて加速度的に核心へと迫ってくる。いずれもキャッチーなメロディを有しているわけではないが、楽曲をトータルでじっくり聴かせるだけの物を持っている。
#5と#6はブルージーなギターロックとしての側面が最も率直に表れている曲だ。バリバリと掻き鳴らされるギターに、畳み掛けるように感情を吐き出していくヴォーカル。特に人種差別をテーマにしていると言われる#6のエモーショナルさは熾烈だ。"Stop!"という叫び、そして一瞬の静寂を置いて続けられる一連の感情の発露は、身を切り血が滲むかのような痛みを伴なって響く。本作の中で最も印象的な曲の1つだ。#5は#6と共通性を持ちながらも、グランドキャニオンのような荒涼とした広大さを思い起こさせ、#2や#3が醸し出していた古い街並みのような情景とは違ったイメージを与える。
#7は耳に深く残るギターのフレーズと、独特のリズムを持った浮遊感の強い曲だ。#2や#3以上に全体的な空気感によって最後まで聴かせていく。#10も#7ほどではないもののそれと似た感触を持っている。続く#11は本作で最も静寂にスポットを当てた曲であろう。そういう意味では、前作の"He Calls Home"と共通するものもあるのだが、#9から静かな曲が連続してしまうため、やや地味な印象を与えてしまうのは否めない。しかしながら後半のヴァースで聴けるブルージーなベースには味があり、ただ聞き流してしまうにはもったいなくもある。"Butterfly"(#9)と"Butterfly (Reprise)"(#12)は対になっており、#9が#12のプロローグ的な関係にあると言っていいだろう。#9はその世界観を連想させながら、ごく淡々と続いていく。そして目の前の扉が開きかけたところで、曲は静かに終わりを告げる。そしてアルバムの最後を飾る#12はその流れを受け、美性をたたえるアルペジオと静かなヴォーカルを乗せながら流れていく。何度も自分に語りかけるようにつぶやき、蝶 -Butterfly- が羽根を広げて羽ばたく姿と、自らがこの世界から飛び立っていく様 -すなわち死- を重ね合わせながら絶叫と沈黙を幾度も繰り返す。そして最後は全てが散り行くかのように重さを引きずりながらアルバムはその幕を下ろす。
感情をダイレクトにぶつける#1に始まり、混沌と混乱の中を切り抜け、#12で全てを無に帰してゆく。コンセプトアルバムではないが、アルバム全体に一貫したトーンが通っており、1枚のアルバムで大きな1つのテーマを扱ってるかのごとき統一感がある。また、歌詞が1stに比べてさらに抽象性が増し、より内省的になったこともそれを印象づけるのに寄与している。音楽的には大きな違いはあるものの、Alice In Chainsの3rdアルバム"Alice In Chains"に近い世界観がある。1曲ごとのわかりやすさがやや弱いという面はあるが、#4や#8のようなインパクトのある楽曲がそれを上手く補っている。ただあえて欲を言うならば、#9~#11の間にたとえば"Mothers Dream"のような起伏に富んだ楽曲が1つあって欲しかったとも思うが。しかしながら、このアルバムからは1stに収録されていたその"Mothers Dream"のオルタナ路線の拡大に留まらず、それをさらに掘り下げて深化したことが強くうかがうことができる。音楽性の完成度から、アルバムを流れる世界観まで、その全てに深みを感じさせてくれるアルバムだ。

"Lucy"のリリース後、バンドはジョン・レノンのトリビュートアルバムに"Steel And Glass"のカバーを提供する。このアルバムには他にRed Hot Chili Peppers, Screaming Trees, Mad Seasonなどが参加しており、作品は10/10にリリースされた。
アルバム"Lucy"からは"Simple Lessons"のビデオがMTVでくり返しオンエアされるが、アルバムは前作ほどのセールスを得られなかった。それでも1996年にはゴールドディスク(50万枚)に認定され、後にプラチナアルバム(100万枚)にまで達した。
アルバムリリースやツアーなど積極的に活動を行っていた彼らだったが、1997年にはケヴィンと共にUncle Dukeを結成したドラマーのスコットが脱退してしまう。バンドは後任のドラマーに、Pearl Jamの元メンバーで1stアルバムの"Ten"に参加したデイヴ・クルーセンを迎える。バンドはデイヴが加入したその日に4曲の新曲を書き上げたという。バンドはそれまでメロディアス・ハードロック系のバンドを手がけてきたロン・ネヴィソンをプロデューサに迎え、ニューアルバムのレコーディングを行う。Candleboxとしての3rdアルバムとなる"Happy Pills"は1998年の7月にリリースされた。
ドラマーに元Pearl Jamのデイヴ・クルーセンを迎えて制作された本作は、実に前作の"Lucy"とは対照的なアルバムに仕上がった。それは同時にこれまでCandleboxに足りていなかった要素の強化と結びついている。アルバム全体の流れ以上に楽曲ごとの存在感が高められ、それぞれの曲においてもメロディアスな面がより強調されている。派手さはないものの、まさしく純然たるアメリカンロックの香りのするアルバムだ。あえてPearl Jamのアルバムにたとえるなら、70年代ハードロックを継承した1stの"Candlebox"は"Ten"に、オルタナティブ色を強めた"Lucy"は"Vitalogy"に、大らかさと落ち着きを持ったアメリカンロックに根差した本作は"Vs."と"Yield"の中間に位置すると言えるだろうか。本作ではこれまで顕著であったブルーズの色合いもいくぶん薄まり、全体的にカラリと澄み切ったサウンドとなっている。もちろんブルーズの要素も見られるのだが、それは前作までのようにダークネスを強調するものではない。むしろBlack Crowesなどに見られる明度の高いものだ。また、本作ではオルガンが効果的に用いられていたり、アコースティックサウンドが大幅に導入されていることも挙げておきたい。それに対して、"Lucy"にあったラフでルーズな感触はかなり弱まっている。しかし、前作で確立したバンドとしてのグルーヴは損なわれておらず、また楽曲の流れの中で感情の高まりを表現する技術は本作でも冴え渡っている。
アルバムは全体的にメロディアスなアメリカンロックを指向しているが、叙情性を意識した曲と温かみのある空気感を重視した曲に大きく分けることができる。前者には#2, #5, #6, #7が当てはまるだろう。タイトルチューンでもある#2は、グランジらしいヘヴィネスと胸を突き刺さるエモーショナルなメロディが絶妙に調和している。本作の中でもかなり大きな存在感を持った曲だ。#6も同じくハードなドライブ感を持って攻めてくる。それに対して#5と#7はあまり重くはなく、深みのあるメロディを折り重ねながら後半にかけて勢いをつけ、感情のダイナミズムを描写していく彼ららしいスタイルだ。特に#5はその魅力が最大限に引き出されている。
メロウな要素が強い曲としては#3, #4, #8が挙げられる。#4の"It's Alright"は間違いなくその代表と呼ぶことができる曲で、春の陽射しのようなほのかな温かみを持ったメロディが映え、これまでには見られなかったCandleboxの新しい一面が映し出されている。#8もそのスタイルを踏襲しているが、こちらはメロディの良さだけでなくスケールの大きさも感じさせる曲に仕上がっている。#3は#4などと共通する美しさと、#5に見られるような叙情性が対峙しているかのような力強さがある。
アルバムの最初を飾る"10,000 Horses"はそのどちらにも属さない、まさしく直球勝負と呼びたくなるようなアメリカンロックだ。大地を踏みしめ、そして荒野を駆けていくような、純粋なアメリカンロックバンドとしてのCandleboxの本作に対する強靭な意志が感じられる。#11は溌剌としたサウンドとメロディが踊り、弾けるようなポップネスが息づいている。しかし決して聴きやすさだけを求めたものではなく、足に絡みつく全ての物を振り切るような力が満ちている。同じく軽快さを見せる#9と並んで、このアルバムの持つ透明感のあるカラフルさを余すことなく表現している。これらの要素は本作で起用したプロデューサーのロン・ネヴィソンによって与えられた効果の1つでもあるだろう。#12はこのアルバムの中ではやや異色で、Led Zeppelin風のブルージーなハードロックと重みのあるグルーヴが融合している。しかしリズムが跳ねていることもあり、沈み込むような暗さは希薄だ。オルガンやエレクトリックピアノも取り入れられており、オーソドックスなハードロックに回帰した印象を抱かせる。#10はメロウなイントロから、エモーショナルで激しいサウンドまで、本作にあるあらゆる要素を混ぜたような不思議な曲だ。
サウンド面でよりストレートなアプローチを見せたのと同じく、歌詞もより直接的でわかりやすくなっている。"10,000 fingers dragging me down... Never wanna slow down."(1万本の指が俺を弱らせるんだ。でもスピードを落としたくない)と歌われる#1では、ファンや周りの人達に対する複雑な思いとそれを越えようとする意欲が示されている。これまでの作品のように相手に話しかけるスタイルも多いが、独り言のように自己完結することは少なく、相手に伝えるという意図がより明確になっている。#2では精神安定剤(=happy pills)にひどく依存しながら生きる相手への言葉が重く伝わってくる。また、本作は#1や#2をはじめとして、ある物事のターニングポイントを描いたものが多い。#5, #6, #10, #12以外の曲は全てそのような視点から書かれていると言えそうだ。ちなみに、#5の"A Stone's Throw Away"は「石を投げて届く範囲」、すなわち「すぐ近く」を意味している。
アルバムごとに違う顔を見せながらも、彼らの作品はそのいずれもが充実した完成度を誇っている。彼らの基盤はつねにブルーズとアメリカン・ハードロックであり、ものすごく広範な音楽性を持っているわけではない。かといって、Stone Temple Pilotsのように特別に器用さを感じさせるバンドでもない。しかしながら、彼らはその音楽性をあらゆる側面から描き出すことができるという柔軟性と、そのときに自分達が出そうとするサウンドを最大限の形で表現するだけの力を持ち合わせているバンドと言えるだろう。
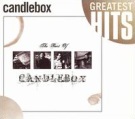
Candleboxは"Happy Pills"をリリースした後、映画"Waterboy"のサウンドトラックに"Glowing Soul"を提供する。このサウンドトラックは1998年11月にリリースされた。バンドは1998年の冬からAerosmithのオープニング・アクトを務めるが、1999年初頭には新たに加入したデイヴ・クルーセンがバンドを脱退してしまう。さらにはベーシストのバーディとギタリストのピーターまでもがバンドを脱退。残されたオリジナルメンバーはヴォーカリストのケヴィンのみとなってしまう。その後、ケヴィンはドラムに元Ugly Kid Joeのシャノン・ラーキンを、ベースに元Digのロブ・レディックを迎えてバンドの立て直しを図る。しかしバンドの継続することは難しく、2000年にはCandleboxとしての活動を停止することになる。
Candleboxとしての活動を終了してから、ケヴィンは自身のプロジェクトとしてKevin Martin & The Hiwattsを立ち上げる。ケヴィンはHoleのメンバーであったエリック・アーランドソンなどと共に曲を書き、アルバム"The Possibility of Being"を2003年の6月3日にリリースする。ギタリストのピーターはRedlightmusicというバンドを結成し、2004年10月19日にアルバム"Redlightmusic"をリリースした。両者のアルバムはいずれも彼らと馴染みの深いケリー・グレイがプロデュースを行っている。
彼らはそれぞれのバンドで活動していたが、2006年にオリジナルメンバーの4人が集まってCandleboxの活動を再開させることを決定する。5月には"Glowing Soul"を含むベスト盤をリリースし、7月から3ヶ月間の北アメリカツアーへと乗り出した。
Other Information
本作からシングルとしてリリースされた曲
本作に収録されなかった曲
本作や1992年のデモテープ等からのアウトテイク