Characters
††:未発表曲・レア曲集
†††:ベストアルバム
††††:ライブアルバム
†††††:その他のアルバム

Soundgarden(サウンドガーデン)の源流は1980年代初期に活動していたThe Shempsというカバーバンドにまでさかのぼることができる。このバンドは後にSoundgardenを共に結成することになるクリス・コーネルとそのルームメイトであったヒロ・ヤマモトの2人によって組まれたものであった。当時はクリスがヴォーカルとドラムを、ヒロがベースを担当していた。その後、ヒロはバンドを脱退し、その後任のベーシストとしてキム・セイルが加入する。ヒロとキム、そして後にSub Popを立ち上げることになるブルース・パヴィットの3人はイリノイ州パークフォレストのリッチイースト高校に通っていた頃からの友人で、高校卒業後に一緒にシアトルのあるワシントン州へと移り住んできていた。
ヒロはバンドを脱退してからもクリスとコンタクトを取り続けており、The Shempsが解散してからすぐにクリスとジャムを始める。そこに間もなくキムもギタリストとして加わり、この3人によって1984年にSoundgardenが結成されることとなった。また、ドラムはThe Shemps時代と同じくクリスが兼任していた。バンド名のSoundgardenはシアトルのアメリカ海洋大気局(NOAA)にある'A Sound Garden'というパイプで作られた彫刻から取って名付けられた。
1985年にはクリスがヴォーカルに専念できるように、スコット・サンドクイストが新たにドラムとしてバンドに加入した。この年の8〜9月にはC/Z Recordsによるコンピレーションアルバム"Deep Six"(1986年3月にリリース)へ参加するため、バンドとしての初レコーディングがIronwood Studiosで行われた。Soundgardenはこのアルバムに"All Your Lies"、"Tears to Forget"、"Heretic"の3曲を提供している。また、この作品はGreen River、Melvins、Skin Yard、Malfunkshun、The U-Menというグランジ黎明期を支えたバンドが多数参加していることでも知られている。
バンドはこのラインナップで1年ほど活動していたが、1986年にはドラムのスコットが家族と過ごしたいという理由からバンドを脱退する。その後任として加入したのが、それまでSkin Yardでドラムを担当していたマット・キャメロンであった。これによって、初期のSoundgardenとしてよく知られているラインナップが完成した。

シアトルのFMラジオ局であるKCMUでDJを務めていたジョナサン・ポーンマンはSoundgardenに興味を持ち、バンドにレコードを出すための資金提供をしたいと申し出る。それに対してキムはすでにサブポップを立ち上げていたブルース・パヴィットと組んでみてはどうかと提案する。このときまでにサブポップはSonic Youth、Wipers、Scratch Acidなどが参加したコンピレーション"Sub Pop 100"とGreen Riverの"Dry as a Bone (EP)"などをリリースしていた。ジョナサンはサブポップがより大きなレーベルになれるよう20000ドルを提供、さらに共同経営者としてブルースと活動を共にすることになる。
Soundgardenはそれにともなってサブポップと契約し、ジャック・エンディーノをプロデューサーに迎えてシアトルのReciprocal Studiosでレコーディングを開始する。そして1987年の7月に初のシングルとなる"Hunted Down / Nothing to Say"を、10月に本EP"Screaming Life"をリリースした。また"Hunted Down"はKCMUのコンピレーションテープにも収録された。このテープはレコード会社によって配給され、Soundgardenがメジャーレーベルの目に留まるきっかけともなった。
Green River、Skin Yard、The Melvinsなど黎明期のグランジを築きあげたバンドの多くは、強い地下臭とテンポを落としたハードコアというBlack Flagのスタイルからの影響を強く受けていた。そして、そこにHR/HMなどの要素を取り込むことで、初期のグランジは作られていった。Soundgardenもその代表格として挙げられるが、彼らはその中でもとりわけ粘り気の強いサウンドを鳴らしていた。
Black Flagからの影響を基盤にしつつ、Led ZeppelinのゴツゴツとしたグルーヴとBlack Sabbathのドロドロとした情念を流し込む。また、Killing JokeやBauhausなどのポスト・パンク/ニューウェイヴ勢からの影響を消化し、Black Sabbath流のドゥーミーなダークネス一辺倒ではなく、独特の薄ら寒さをサウンドに溶け込ませることにも成功している。そして、それをサイケデリックな粘りによって固めていく、初期のSoundgardenの音楽性をまとめるならこんなところだろうか。 後のアルバムでは王道Hard Rock/Heavy Metalへの接近も見せる彼らではあるが、本作ではギターのアレンジをはじめ、全体的にノイジーさを強調した作りとなっている。
そのスタイルが最も如実に表現されているのが、本作のハイライトでもある#1と#4である。#1はBlack Flagのようにスラッジーでありながらも、ゴリゴリとしてなおかつ粘りがある。一方の#4はイントロや間奏こそサバスのようにドゥーミーだが、全体としては浮遊感のほうが強調されている。#2はパンキッシュだが、その中に彼ら独特の薄ら寒さや初期の頃のScreaming Treesとも共通するようなサイケデリアが垣間見える。#3はテンポを落としたハードコアそのものといったところだ。 本作の後半を飾る#5と#6はいずれもヴォーカルの存在感はあまり大きくなく、サウンド面での実験的な要素が強く見られる。#5はサイケ感と中期以降のLed Zeppelinに通じる感触が際立っており、#6は70年代的なブルージーなハードロックを聴かせる。
後に急成長を見せるクリス・コーネルのヴォーカルも本作ではまだ粗削りな感が強い。#3では彼としては珍しいひたすら叫びまくる歌唱を聴くこともできる。
歌詞の面では彼らの特徴でもある哲学的な香りを感じさせるものがアルバムの後半を中心にいくつか見られる。#6ではジャック・エンディーノが買ったレコーディング用テープにもともと入っていた牧師の説教をいくつかの場面でそのまま利用するといった工夫もなされている。これとクリスが歌詞を書いた箇所とを対比させてみるのも面白い。また本作では#1などで切迫感を強調した歌詞も見ることができる。
Soundgardenにとって最初の作品となった本作だが、ここで既に初期のグランジとしての1つのスタイルが明確に確立されている。また#1や#4をはじめ質の高い楽曲が見られ、バンドの持つポテンシャルの高さも十分にうかがい知ることができる。この時代のグランジを代表する作品の1つとも言えるだろう。

バンドは初の作品となった"Screaming Life EP"のリリースに続いて、1988年にはシアトルのMoore Theatreで2枚目となるEPのレコーディングを開始する。プロデューサーにはScreaming TreesやBeat Happeningなど、シアトルのバンドのレコーディングを手がけていたスティーブ・フィスクが迎えられた。そうして制作されたEP"Fopp"は同年8月にリリースされた。
"Screaming Life"に続く2枚目のEPである本作では、収録曲が4曲だけということもあり、前作と比べて作品としての統一感をあまり感じさせない構成となっている。サウンドの持つ全体的な雰囲気は前作の延長線上にあるものの、曲単位で見ると遊び心が強く見られるのが特徴だ。
タイトルチューンでもある#1はR&B/FunkバンドであるOhio Playersの1975年の曲のカバー(オリジナルはアルバム"Honey"に収録)だ。ギタリストであるキム・セイルがR&B色の強いこの曲をAC/DCぽく仕上げたいと考えて作られたとのことである。原曲のアレンジを基本にしつつも、ロックとしての主張を強めたサウンドになっている。#2は同曲にプロデューサーであるスティーブ・フィスクがダブミックスを行ったものだ。
#3は彼らの曲としてはかなり異色で、Mudhoneyが演奏しても全く違和感がないほどのガレージ・ロックンロールとなっている。Black Flag由来の地下臭の漂うハードコア路線とは一線を画している。#4はGreen Riverの曲(オリジナルはEP"Come on Down"とアルバム"Rehab Doll"に収録)のカバーだ。Mudhoneyを連想させる#3から、その前身バンドであるGreen Riverの曲へと展開するこの流れはなかなか興味深い。アレンジに大きな違いはないものの、クリス・コーネルのソウルフルなヴォーカルが入ることで、原曲よりも力強さをより主張した仕上がりになっている。
オリジナル曲が1曲だけということもあり、明確な方向性を持って作られた作品という印象は前作の"Screaming Life EP"と比べるとやや薄い。あくまで"Fopp"のカバーバージョンを収録するために作られた作品という色合いが強いと言えそうだ。一方でバンドの持つ少し違った側面も見ることができ、そのような視点で見るとなかなか面白い作品でもある。

1987年に"Screaming Life EP"をリリースして以降、Soundgardenはメジャーレーベルからも声をかけられるようになっていく。しかしバンドはメジャーレーベルではなく、Black Flagのギタリストであるグレッグ・ギンが立ち上げていたインディーレーベルのSST Recordsと1988年に契約し、初のフルレンスアルバムの制作へと取りかかった。バンドはSSTサイドからの提案にしたがって"Fopp EP"のレコーディングでエンジニアを務めたDrew Canuletteをプロデューサーに迎える。そして1988年の春にシアトルのDogfish Mobile Unitとオレゴン州ニューバーグのDogfish Studioでアルバムのレコーディングが行われた。1986年に"Deep Six"に提供した"All Your Lies"の新バージョンも含んだこのアルバムはキムの提案に沿って"Ultramega OK"と題され、1988年10月31日にリリースされた。
しかしレコーディングの際のバンドとプロデューサーのDrew Canuletteの関係は思わしくなく、バンド側にはアルバムのプロダクションに対して大きな不満が残ることになった。そこでバンドは"Screaming Life EP"をプロデュースしたジャック・エンディーノにアルバムを改めてミックスしてもらうことを考え、実際に"Flower"のラフミックスを制作する作業などが行われた。しかし最終的にはアルバムを再びプレスするための時間と経済的な問題を考慮して断念された。
また、バンドはこれとほぼ同時期にSub Popのコンピレーションアルバム"Sub Pop 200"へ提供するために"Sub Pop Rock City"のレコーディングも行った。レコーディングはシアトルのReciprocal Recordingで、ジャック・エンディーノがプロデュースを務めて行われた。この"Sub Pop 200"には他にNirvana、Green River、Mudhoney、Screaming Trees、Tadなどシアトルシーンを支えた多くのバンドが参加しており、1988年12月にリリースされた。
Black Flagの影響を土台にしながら、そこにHR/HMやサイケなどの要素を溶け込ませていく。この時期のSoundgardenが突き詰めてきた方向性の1つの到達点が、初のフルレンスアルバムである本作と言えるのではないだろうか。
ダークな質感を持ったミディアムテンポのハードコアから、Led ZeppelinやBlack Sabbathの世界を彼らなりに咀嚼して表現した曲、さらにはねっとりとしたブルーズロックまで、一見するとこれまでの路線をストレートに受け継いでいるようにも思える。しかしながら、曲のタイプはそれぞれ違えど、作品全体を通してこれまで以上におどろおどろしい雰囲気が強調されており、表現しようとする世界のイメージがより明確にされていることに気が付く。住む人を失い、誰も寄り付かなくなった古ぼけた洋館に真夜中に迷い込んでしまったかのような薄気味悪さ、とでも表現できるだろうか。
その雰囲気が最も溶け込んでいる曲としては#6が挙げられるだろう。当時の彼らにしては珍しくアコースティック・ギターから始まる曲で、「重い」「暗い」という以上に奇妙な冷たさが流れていることを感じさせられる。また、彼らの基本のスタイルでもあるダークでテンポを落としたハードコア指向の曲としては#2、#7、#11を挙げることができる。この方向性はこれまでの作品でも見られたのだが、本作ではピンと張り詰めた緊張感や疾走感が強調されていることがわかる。たとえば"Deep Six"に収録されていた"All Your Lies"と同曲を改めてレコーディングした#2を聴き比べてみると、その感触の違いを読み取ることができるだろう。#7ではベースのヒロ・ヤマモトがヴォーカルをとっていて、おどろおどろしいベースラインと彼の狂気に満ちたシャウトが本作の持つ個性を強烈に印象付ける。いかにもBlack Sabbathな#4においても、ただドゥーミーに仕上げるだけではなく、やはり本作の持つ空気感を表現しようとする姿勢が見られる。Black Sabbathを指向しつつも、Led Zeppelinのゴリゴリとした感触が随所に見られる点も興味深い。また、#3の"665"と#5の"667"によってサバス色の強いこの曲をはさむことで、「獣の数字」として知られる「666」を連想させるといった工夫も凝らされている。
#9は1950年代から1970年代にかけて活躍した黒人ブルーズシンガーであるHowlin' Wolfのカバー(オリジナルは1959年のアルバム"Moanin' in the Moonlight"に収録)だ。そして#12ではそれに負けじと初期のLed Zeppelinそのものといったブルーズ・ハードロックを聴かせる。また、その中にもサバスっぽさがチラリと覗くのも面白い。もちろんいずれの曲も本作の持つ感触とうまく噛み合っている。ちなみに#9の最後に挿入されているのはSonic Youthの"Death Valley '69"(オリジナルはアルバム"Bad Moon Rising"に収録)だ。
このアルバムのハイライトでもある#1は、Led Zeppelinのゴツッとした側面を前面に押し出した曲だ。うっすらとしたサイケ感と浮遊感があるものの、気味の悪さのようなものは強くなく、ストレートなアプローチを見せる曲と言えそうだ。#10はヒロによる曲で、このアルバムの中でもとりわけインディー臭が強く漂ってくる。この曲で聴けるチープながらも味のあるギターフレーズが耳に残る。そして#8では、後に彼らが得意とする変拍子が登場している。3/4と4/4を短い間隔で行ったり来たりすることで奇妙な空気が作り出されている。アルバムの最後を飾る#13はジョン・レノンの曲のカバー(オリジナルはアルバム"Unfinished Music No.2: Life with the Lions"に収録)だが、単なる無音である。
歌詞の面では物事を俯瞰的に見てそれをやや抽象的に描写するというクリスのスタイルがより確立されてきている。退廃的な女性を描いた#1、ナチスをこき下ろした#10、家庭における親子の問題を書いた#4などがその中でも印象に残る。また、この時期のクリスの歌詞はパーソナルな視点から書かれたものが少ないのも特徴だ。たとえばPearl Jamのエディ・ヴェダーがアルバム"Ten"で書いた歌詞と#4を比較すると、共通した問題を扱いながらもその視点の違いが見えてくる。"665"ではヘヴィメタルなどにおけるサタニズムをパロディにしており、サタンのかわりにサンタ・クロースを崇拝する歌詞を書くなどの遊びも見られる。
Soundgardenにとって初のフルレンスアルバムとなった本作では、バンドがこれまで打ち出してきた音楽性に対して一定の完成を迎えることに成功したと言えるだろう。バンドとしてもそういった感触を得たのだろうか、次作以降は本作までに培った諸要素を取り入れながらも、さらに違ったスタイルを模索することでより音楽的に進化するべく歩みを進めることになる。それらの点から見ると、本作は初期のSoundgardenに区切りをつけた作品ともとらえられるだろう。
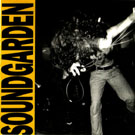
1stフルレンスとなる"Ultramega OK"をリリースしたSoundgardenは、そのオープニングトラックでもあった"Flower"から彼らにとって初となるミュージックビデオをMark Miremont監督のもとで制作する。これはMTV 120Minutesでレギュラー放送されることになった。
さらにバンドは間を置かずに次のアルバムの制作へと取りかかっていく。しかしこの頃には既にベースのヒロがバンドに距離を置き始めており、これまでと同様の流れでソングライティングを行うことが困難な状況となっていた。そのため、アルバムの収録予定曲の大半をクリスが単独で書き上げるという形になった。その後、バンドは1988年12月から翌年の1月にかけてシアトルのLondon Bridge Studiosでテリー・デイトをプロデューサーに迎えてニューアルバムのレコーディングを行う。プロデューサーを務めたテリーとの関係は良好で、前作のような軋轢は起こることはなかった。
また、バンドは1989年の春から"Ultramega OK"のアメリカ国内ツアーをスタートさせる。さらに同年5月からはヨーロッパにおいて初の海外ツアーも行った。このツアーが終了して間もなく、バンドはメジャーレーベルであるA&Mとサインする。こうして彼らは後にグランジと呼ばれることになる当時のシアトルバンドの中で最も早くメジャーレーベルと契約したバンドとなった。そして9月には既にレコーディングを済ませていたアルバムが"Louder Than Love"と題されてA&Mからリリースされた。このアルバムタイトルは「俺達は○○よりラウドだぜ」といったHR/HMバンドがしばしば行うような主張を言葉遊び的に利用したものだということだ。
メジャーレーベルであるA&Mと契約してからの初めてのアルバムとなった本作では、過去の作品とはスタイルが大幅に変化している。これまで強く見られたBlack Flagのような地下臭は薄くなり、一方でLed Zeppelinの厚みのあるハードロックへと接近、そこにThe Melvinsの腹にズシッとくるヘヴィネスを加えたサウンドになっている。また、彼らの特徴の1つであったサウンドの持つ粘度は本作でさらに強まり、全体的にミディアムテンポの曲がより目立つようになった。また、これまでは(ギターの)キム・セイルがメインの作曲者であったが、本作からはクリスが大半の曲を書くようになっている。これも彼らの音楽性が変化した大きな理由の1つと言えよう。
Led Zeppelinの香りのする粘り気のあるハードロックとクリス・コーネルの組み合わせといえば、Soundgardenの解散後に彼がRage Against The Machineのメンバーと結成したAudioslaveが思い起こされる。たしかに共通するものもチラホラと見受けられるものの、本作の持つ異様なまでにベトついた粘り気やサイケ感は正統派としての色合いが強かったAudioslaveと異なる面もやはり多い。クラシックなハードロックに接近しつつも、独自の個性を発揮しているところが本作の面白みでもある。
本作の特色でもあるLed Zeppelin色がとりわけ強い曲としては#1、#2、#5などが挙げられる。粘りのあるサウンドとヴォーカルを聴かせる#1から、そこにさらに浮遊感やサイケデリックな感触を流し込んだような#2へと続く流れは、アルバムの方向性を強く印象づけてくれる。#5は同じ方向性を見据えつつも、ポップでとっつきやすいハードロックとして仕上がっている。この#2と#5は本作の中でも特に完成度の高い曲と言える。#11や(シングルとしてもリリースされた)#7もZEPの要素を色濃く感じさせる曲だが、こちらは同じリフをひたすら反復することによってトリップさせるようなサイケ感の強いサウンドを生み出している。重みのある粘っこさで押し込むというよりは、一歩引くことによって生まれる良さがいかされている。#11は後にGuns N' Rosesがアルバム"Spaghetti Incident?"にてカバーしている。#10もZEPっぽさを感じさせるが、粘り気がやや弱く、エネルギーを外に放射するような感覚がある。次作の"Badmotorfinger"の後半に見られる作風に通じるものもあると言えそうだ。
それに対して#3、#4、#8はThe Melvinsを思わせるヘヴィネスやBlack Sabbathの持つドゥーミーな世界をより指向している。特に#3はThe Melvinsに通じる重さをテンポを徐々に速めながらボディーブローのように打ち込んでくる。本作におけるヘヴィネス路線の代表といっていい曲だ。#4はドゥーミーな重さが6/8のリズムとうまく相まって横にユラユラと揺れるようなグルーヴを生み出している。気味の悪いハーモニクスから始まる#8は前作の"Beyond The Wheel"にも通じるような、重さと切れ味の鋭さが同居したサウンドを聴かせる。#9では前作に多く見られたおどろおどろしいサウンドとベースラインを聴くことができる。同じくヒロ・ヤマモトが書いた#4、#8にも共通するものが見られる。#6は本作では唯一といっていいアップテンポでパンク色の強い曲だ。アグレッシブなサウンドと薄気味の悪さが同居したサウンドが印象深い。#12はこの#6をモチーフにしたアルバムのエピローグ的な曲だ。
また、この作品においてとりわけ目立っているのが変拍子の多用である。前作では"He Didn't"ぐらいでしか見られなかったが、本作ではより多くの曲で変拍子が使われている。#1の6/4などはまだ大人しいほうで、#5では4/4と9/4が入り組んで展開され、オーソドックスに見える#9でも後半で7/4の拍子が登場する。そして極めつけは#8で、4/4 → 6/4 → 11/8 → 14/8 → 6/4とコロコロと変わりながら、最終的に9/8に行き着くという目まぐるしい変化を見せる。サウンドのスタイルにおいては伝統的なハードロックに近づきつつも、彼らが決して一筋縄でいくようなバンドではないことを如実に物語っている。
歌詞についてはこれまで同様に抽象的ではありながらも、いくつかの曲で歌詞の持つ主張がより明確に伝わるようになっている。また、#3や環境問題について書かれた#2では社会的な問題も扱われている。一方、死をテーマにして書かれた#9などでは、前作までにも見られたクリスらしいスタイルも見ることができる。#6はクリスと友人2人の間で実際に起きた話で、一方の友人がもう一人の友人であるケヴィンの母親と深い関係になったことから友人関係が完全に壊れてしまったことが書かれている。"Fuck"という言葉が多用されていることでも知られる#11は、80年代のグラムメタルバンドの書く歌詞を皮肉を込めてパロディ化したものだ。わざとストレートな表現を用いることで、「連中の歌っていることって、表現こそボカしてるが結局はこういうことだろう」と痛烈に揶揄している。このアルバムの収録曲の中で唯一クリスが歌詞を書いていないのが#8だが、この曲には面白いエピソードがある。#8の作曲者であるヒロはこの曲を書いた後、当時の恋人であったKate McDonaldからのメッセージが書かれた紙に歌詞を書き、それをクリスに渡したのだという。するとクリスはKateのメッセージが書かれた側を見て、それを歌詞だと勘違いしてしまったとのことだ。この曲の作詞のクレジットがKate McDonaldとなっていて、その内容が曲の雰囲気に似つかわしくないラブソング風になっているのはそのためである。
メンバー間のコミュニケーションに変化が起きたことから事実上クリスが主導することとなった本作だが、結果としてSoundgardenの新しい方向性を打ち出す作品ともなった。また本作はメジャーレーベルからの初作品でもあったが、レコーディングはA&Mとサインする前に行われたため、サウンドの面ではまだ粗さも見られる。そのため、本作で得た諸要素の整合性をより高めたサウンドは次作の"Badmotorfinger"にて完成することになる。

メジャーレーベルからの初のアルバムとなった"Louder Than Love"は最高位としては108位にとどまったものの、彼らにとって初めてBillboard 200にチャートインした作品となる。Soundgardenはアルバムリリースにともなうツアーに出ることになっていたが、その1ヶ月前になってベースのヒロがバンドを脱退してしまう。前作の制作過程に自分があまり関わらなかったことへの不満や、大学(Western Washington University)に戻って物理化学の修士課程を修了したいと考えていたことがその理由だった。バンドはNirvanaに一時的に加入していたジェイソン・エヴァーマンを新たにベーシストとして迎え、1989年12月から翌年3月までカナダのメタルバンドであるVoivodのオープニングアクトとして北アメリカツアーへと乗り出した。このツアーの初期と後期にはFaith No Moreも彼らとともにオープニングアクトを務めていた。
そしてクリスがツアーから帰ってきた3月19日、クリスのルームメイトでもあったMother Love Boneのアンドリュー・ウッドがオーヴァードースによって死去する。クリスはその数日後にはSoundgardenのヨーロッパツアーへと旅立つが、その中でアンドリューに捧げるために"Reach Down"と"Say Hello 2 Heaven"を書き上げる。この2曲は後にMother Love Boneの元メンバーとSoundgardenのクリスとマットによるアンドリュー追悼のためのプロジェクトであるTemple of the Dogへと繋がっていく。また、4月には"Hands All Over"のシングルB面として収録するためにThe Beatlesのカバーである"Come Together"のレコーディングをプロデューサーのジャック・エンディーノとともに行った。ヨーロッパツアーが終わった直後に、人間関係が上手く行かなかったことを理由にジェイソンが解雇されたため、これがSoundgarden時代に彼が参加した唯一のスタジオ音源となった。ジェイソンはSoundgardenからの脱退後、Mind Funkというバンドに加入することになる。
また、同年5月には彼らがサブポップ時代に残した"Screaming Life"と"Fopp"の2枚のEPが、"Screaming Life / Fopp"として1枚にまとめられたうえで新たにリリースされた。また、その約10日後にはA&Mから1989年12月にロサンゼルスの"Whisky a Go Go"で行われたライヴの映像を収めたビデオ"Louder Than Live"もリリースされた。
サブポップ時代にリリースした2枚のEP("Screaming Life"と"Fopp")を1枚にまとめたのが本作の"Screaming Life / Fopp"である。#1〜#6は最初のEPである"Screaming Life"から当時の曲順どおりに、#7〜#10は2枚目のEPである"Fopp"から曲順を入れかえて収録されている。"Screaming Life"と"Fopp"はいずれもCD化されていないと見られるが、本作には2枚のEPの収録曲が全て含まれているため、この作品さえ入手しておけば十分と言うことができよう。

ヒロ・ヤマモトの後任として加入したジェイソン・エヴァーマンを解雇したため、バンドは新たなベーシストとしてベン・シェパードを迎えることになった。ベンはヒロが脱退した際に行われたSoundgardenの新たなベーシストを選ぶオーディションにも参加していたが、当時は採用されなかったという。新たにベンを迎え入れたバンドは、ドラムのマットが書き上げた"Room a Thousand Years Wide"のレコーディングをプロデューサーのStuart Hallermanとともに行う。この曲はサブポップからシングルとして1990年の9月にリリースされた。また、同曲はアルバム"Badmotorfinger"にも収録されているが、それは今回のシングルバージョンとは別にレコーディングされたものである。
また、バンドは1990年7月から9月にかけてDanzigのオープニングアクトとしてアメリカツアーを行った。そして10月にはアルバム"Louder Than Love"からの2枚のシングル"Loud Love"と"Hands All Over"の収録曲をまとめたEPである"Loudest Love"を日本向けにリリースする。このEPは後にアメリカでもリリースされることとなった。このEPに収録されている"Heretic"は映画"Pump Up the Volume"のサントラ(1990年8月リリース)に、"Fresh Deadly Roses"はA&Mのコンピである"Pave the Earth"(1990年6月リリース)にも収録されている。また、この年には1stアルバムの"Ultramega OK"がグラミー賞のBest Metal Performanceにノミネートされている。
もともと日本向けのEPとしてリリースされた本作は、言うなれば前作である"Louder Than Love"の主要曲と同アルバムからカットされたシングルのB面集といった性質のものである。本作に収録されているのは前作から3曲(#1〜#3)、"Hands All Over"シングルのB面から2曲(#4と#5)、"Loud Love"シングルのB面から2曲(#6と#7)となっている。このうち、#4はイギリス盤の4曲入りシングルにのみ収録されていたものだ。
また、本作は前作の"Louder Than Love"から派生した作品ということもあり、レコーディングは#5を除いて全てアルバムのセッション時に行われたものとなっている。#5だけは("Screaming Life / Fopp"のLittle Biographyに記したように)1990年の4月にレコーディングされている。
そのため、基本的な音楽性は前作とほとんど違いはない。#4はバンドの最初期の頃に"Deep Six"コンピレーション(1986年リリース)に提供した曲を新たにレコーディングしたものだ。当時のバージョンに比べると前作の特徴である粘り気が強調された作りになっている。#5はThe Beatlesの曲のカバー(原曲は1969年のアルバム"Abbey Road"に収録)だが、テンポを落としたうえでズッシリとしたヘヴィネスが効かされている。#6は前作と同時期に書かれたもので、アルバムからの純然たるアウトテイクと言える曲だ。サイケデリックな浮遊感が大きく強調されており、Soundgarden流のヘヴィサイケとして完成している。#7は前作に収録されていた曲にスティーブ・フィスクがダブミックスをほどこしたものだ。スティーブは自身がプロデューサーを務めたEP"Fopp"でもそのタイトルチューンのダブミックスを行っている。#1〜#3は前述したように、前作に収録されているのと全く同じテイクである。
既発曲とそのリミックスで収録曲の半分以上が占められていることもあり、入門的な作品としてオススメするのはさすがに難しいだろう。しかし#6をはじめ注目に値する曲もあるため、Soundgardenに関心を持っている人なら手に入れておいて損はないだろう。





Other Information
本作からシングルとしてリリースされた曲
本作に収録されなかった曲